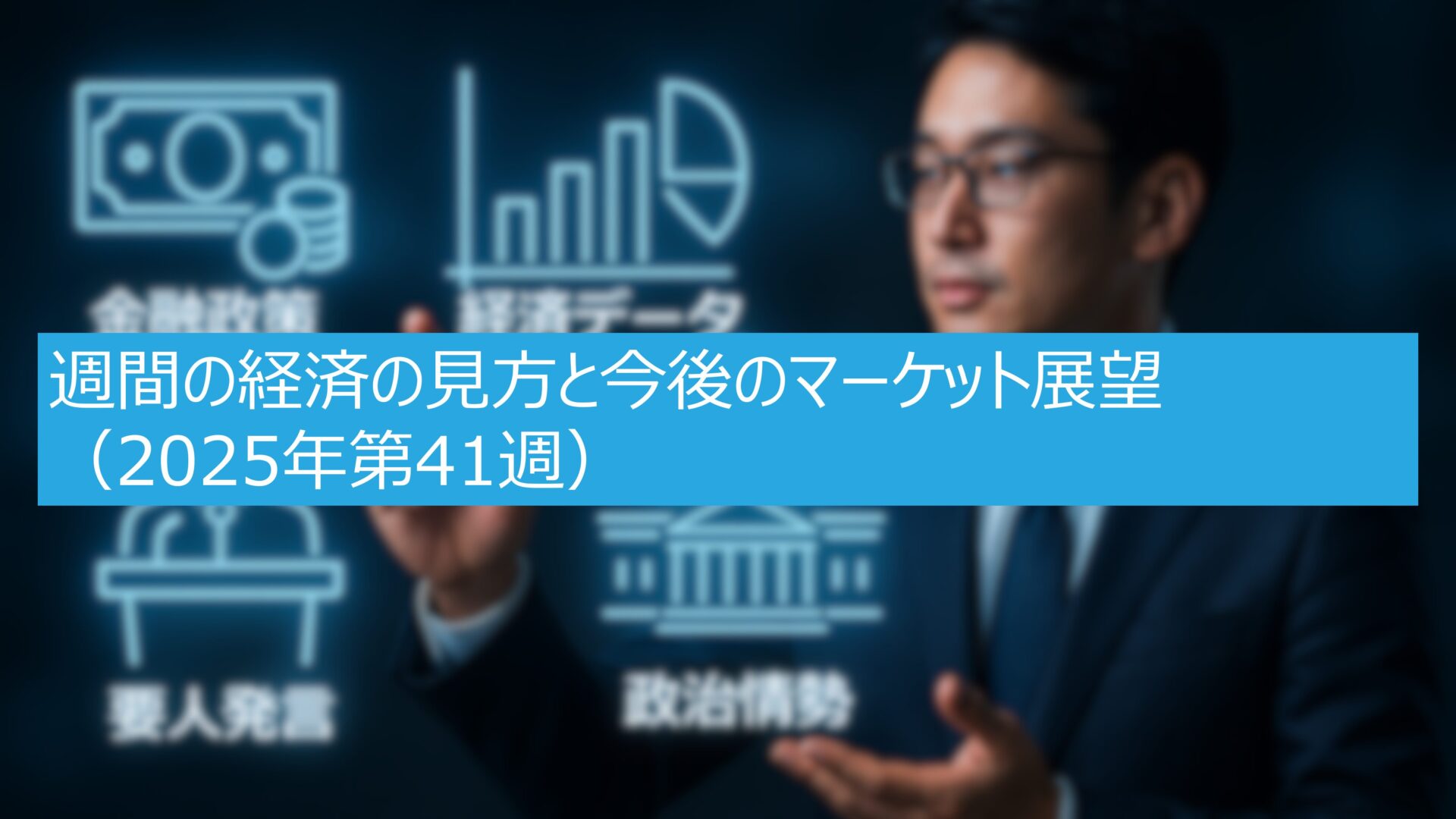2025年10月上旬のマーケットは、米国の政府機関の一部閉鎖によるデータ空白と政策期待の綱引き、日本における新政権の誕生による急速な円安圧力、そしてAIインフラ投資の継続という、複数の大型テーマが交錯する局面でした [1, 2]。投資家は、株と金が同時に上昇する現象に見られるように、リスクを取りつつも、インフレや政策の不確実性に対するヘッジ(分散)を厚くする姿勢を強めています [1, 3-5]。
I. 米国経済と金融政策:利下げ志向とデータ空白のジレンマ
政府閉鎖と重要統計の遅延
米国では、政府機関の一部閉鎖の影響により、本来10月3日に公表予定だった9月雇用統計やCPIなど重要統計の公表遅延が発生しました [6-8]。この「統計空白」は、FRBの次回判断材料を一時的に不足させ、市場の不確実性を高める要因となりました [1, 6-8]。しかし、NY連銀のウィリアムズ総裁は、公的統計が遅れても、民間データで動向把握は可能であるとの見解を示しています [3, 6]。
FRBのスタンスと利下げ観測の継続
9月のFOMC議事要旨が公開され、年内の追加利下げが妥当だと考える参加者が多数だったことが確認されました [6, 9]。ウィリアムズ総裁も年内の追加利下げ支持に言及し、関税がインフレに与える影響は想定より小さく、労働市場の減速リスクを重視する姿勢を強調しています [3, 6, 7]。この発言は、金利低下(バリュエーション押し上げ)観測を支える材料となりました [6, 7]。
しかし、議事要旨にはインフレへの警戒から利下げ見送りを主張する声も併記されており、FRBの政策運営には「利下げ志向とインフレ警戒」という二律背反の構図が残っています [9, 10]。統計の欠落は、FRBがデータ不足のなかで拙速に動かず、物価鈍化を待つ「遅く、慎重」な姿勢を強めると意識されています [9, 10]。
消費マインドと家計信用の減速
米ニューヨーク連銀の消費者調査では、1年先の期待インフレ中央値が3.38%へと3か月連続で上昇しており、特に低所得者層(世帯年収5万ドル未満)でインフレ懸念が強い傾向が示されました [5]。これは金利低下観測を抑制しうるソフトデータであり、株式市場には重しとなる可能性があります [5]。
一方、高金利下での家計の慎重化を示すシグナルも出ています。8月の米消費者信用残高は前月比+0.1%にとどまり、特にリボ払い(クレジットカード)の伸びが前月の+10.3%から▲5.5%に急減速しました [5]。ただし、個人消費の基調はまだ底堅いとの見方も併存しています [5]。
また、米国ではリセッション(景気後退)を伴わない利下げが進行中との見方が共有されており [11]、従来の景気後退型利下げとは異なるセクターパフォーマンス(半導体、ソフトウェア、割安な消費関連の相対優位)が示唆されています [12]。
II. 日本の政治・金融政策と株式市場
高市新総裁の誕生と政策期待
自民党総裁に高市早苗氏が選出されたことで、市場は「積極財政・円安容認的」な政策への期待を背景に、初期反応として株高・円安が意識されました [13, 14]。新政権の政策メニュー(「責任ある積極財政」や年収の壁引き上げなど)は需要下支えへの期待を通じて、株式のリスク選好を強めました [12]。
しかし、市場の関心は短期的な期待先行から、中期的な「政策実行力の現実解」へとシフトしています [13]。財源説明や日銀とのコミュニケーション、与党間の整合性の確保が、“期待の賞味期限”を測る上での厳格な評価軸になると指摘されています [12, 15]。高市総裁は政府・日銀の2013年アコードの直ちの見直しは不要としつつ、行き過ぎた円安を招く意図はないと発言しています [16]。
為替:円安の持続要因と臨界点
円相場は、新政権への政策期待や日銀の利上げ後ずれ観測(10月追加利上げ確率は総裁選後に約56.5%から2割程度まで低下)を背景に円売りが加速し、一時1ドル=152円台と約7か月半ぶりの水準をつけました [14, 17]。
専門家は、円安継続の要因として、日本の実質金利が極めて低いこと [11]、米国の利下げが「正常化色」が強く景気後退色が薄いこと [11]、そして新政権の「責任ある積極財政」への思惑などが複合的に作用していると整理しています [18]。
一方で、市場は「円安の臨界点」を探る局面にあります [16, 19]。短期的には150円台前半〜半ばを中心とした推移が予想されるものの [20]、中期的には米消費の鈍化や米長期金利低下による金利差縮小、あるいは日本側の物価・為替に対するスタンス変化などから、過度な円安追随は警戒されています [10, 19, 21]。
国内株式市場の構造と課題
日経平均は最高値更新の流れの中で、AI半導体関連や円安メリット銘柄が相場を押し上げています [3, 4]。年内に5万円台の試しも視野に入るという強気な見通しも示されています [3]。
しかし、上昇の「幅広さ」にやや物足りなさが残り、寄与度の高い大型テーマ株に偏重しているという指摘があります [3, 4]。株式市場は「期待先行のバリュエーション拡大」がドライバーとなっており [20]、既にバリュエーションは小泉政権期の旺盛な水準に接近しているため、グロース一極からの分散が必要との声が目立ちます [10, 20, 22]。
日本の景気・賃金動向
日銀の「地域経済報告(さくら)」では、9地域中8地域の判断が据え置かれ、景気の底堅さがにじむ内容でした [23]。企業ヒアリングからは、AI関連や省人化投資をはじめとする設備投資意欲の底堅さも確認されています [23]。
しかし、家計の実質購買力回復には時間がかかっています。内閣府の8月景気動向指数(一致CI)は2か月連続で悪化 [24]。また、8月の実質賃金は前年同月比▲1.4%とマイナスが8カ月連続となり [19]、物価高の負担が勝る構図が続いています [10, 19, 24]。可処分所得の実感が伴わない限り、消費の“広がり”は限定されやすいというのがマーケットの共通認識です [10, 19]。
III. グローバル市場の主要テーマと構造的変化
AI・半導体サイクルとサプライチェーン
AI投資サイクルは引き続き強力で、世界景気の下支え要因であり続けています [18]。
- **NVIDIA(エヌビディア)**:CEOは次世代GPU「Blackwell」への超過需要を強調し、AI向け半導体の引き合いが直近半年でさらに増勢であると発言しました [8, 18]。
- **AMDとOpenAIの大型契約**:AMDはOpenAIと大型供給契約を締結し、OpenAIは複数年でAI半導体を合計**6GW相当**購入する計画が報じられました [23]。契約進捗に応じてAMDの株式の一部(最大発行済み株式の10%に相当する新株予約権)がOpenAIに付与される枠組みも示され、AIインフラの中期的ひっ迫感とエコシステムの再編を印象づけました [23]。
IMFはAIの急拡大について、ITバブル期に近づく兆しがあるとして、「急な調整」への注意を促しています [10, 18]。国内目線では、先端半導体の増産が、製造装置・素材など上流の日本企業への需要波及につながる構図は不変であり、国内関連のキャッチアップ余地に注目が集まります [8, 23]。
コモディティと安全資産の台頭(金・銀)
投資家がリスクを取りつつもヘッジを厚く積む現在の地合いを象徴し、金・銀といった貴金属の強さが目立ちました [3, 25]。
- **金**:金先物は大台の4,000ドルを初突破し、年初来の上昇率が50%超となりました [17, 26]。ドル高局面でも金が買われるのは、インフレ期待の粘着性と地政・政治要因が複合しているためです [5]。
- **銀**:銀の現物価格も一時「1トロイオンス50ドル」の大台に乗せ、1980年以来の水準となり、金に続く牽引役との見方が広がりました [25]。
株と金が同時に上がる構図は、ITバブル期のように「株だけが独走した」局面と異なり、投資家がインフレや政策の不確実性に備えて分散しているサインと解説されています [3, 4, 17, 25]。
EV・自動運転と規制リスク
米道路交通安全局(NHTSA)は、テスラのFSD(高度運転支援)で58件の不安全挙動を把握し、対象を約288万台とする新たな調査を進めていると報じられました [25]。これは、自動運転の商用化に対する規制の視線が一段と厳格化していることを示唆し、テック主導の成長期待に対する“もう一つのリスク”を突きつける材料となりました [25]。
テスラはモデルY/モデル3の廉価版(4万ドル以下)を投入し、補助金縮小下の需要喚起を狙いましたが、市場の初期反応は厳しく、株価は4%安となりました。数量拡大とマージン維持の両立における価格弾力性が焦点です [17, 27]。
資源・サプライチェーンの地政学リスク
中国の輸出規制強化観測を受け、米国のレアアース関連が一斉高となりました [25]。供給網の地政学リスクが再燃すれば、素材・半導体・EVなど広範な産業のコストや投資計画に波及する可能性があります [25]。中長期では、米国内供給網強化に資本が向かいやすい地合いが意識されます [25]。
脱炭素ビジネス(バイオガス)の現場
米国のVanguard Renewablesは、食品廃棄物と家畜ふんを原料にバイオガスを製造する分散モデルを採用しています [22]。酪農家の敷地にプラントを設置し、大学と20年の長期供給契約を結ぶことで、需要の“長期安定性”を確保している点が特徴です [22]。資本面ではブラックロックが出資しており、政策の逆風があっても、長期契約と多角化が事業の耐性を高めるという示唆が重要です [22]。
IV. 主要企業の決算と個別動向
米国企業決算の初動
7–9月期決算シーズンが始まり、初弾は堅調なスタートを切りました [1, 4]。
- **デルタ航空(DAL)**:増収増益を達成し、プレミアム需要が業績を牽引しました [6]。通期EPSは従来予想の上限程度との見通しです [6]。高収益のプレミアム座席拡充戦略が収益と株価を下支えしています [8]。
- **ペプシコ(PEP)**:北米飲料の回復で売上・EPSが予想を超過しました [6]。しかし、値上げの長期化でスナック部門の需要鈍化が響き、3四半期連続の減益見通しとなっており [27]、アクティビストのエリオット参入による経営改善要請への市場期待が焦点です [27]。
- **オラクル**:クラウド部門の利益率が予想を下回るとの報道で一時大幅安となり、AI関連の主力銘柄の割高感とセンチメントの変化を象徴しました [26]。
日本の小売大手決算と価格転嫁
国内大手の決算(ファーストリテイリング、セブン&アイHD)では、「価格転嫁の可否」が明暗を分ける焦点となりました [13, 28]。
- **ファーストリテイリング**:通期で2桁増益を達成し、国内売上はアパレルとして初の1兆円超えとなりました [16]。円安や人件費・物流費の上昇を踏まえ、価格の適正化を進める方針を示唆しており、グレーターチャイナの構造改革が収益率改善の鍵です [16]。
- **セブン&アイHD**:中間期は増益ながら、国内コンビニの鈍さを映し通期の営業利益見通しを下方修正しました [16]。物価高による節約志向への対応や、商品力・来店動機の再設計が課題とされています [16]。
前回決算の復習では、内需では「値上げ転嫁力のある業種」で収益性改善が目立った一方、価格転嫁が難しい食品関連は苦戦したと整理されています [27, 28]。
その他の企業・産業トピック
- **Apple**:2022年のiPhone 14から衛星経由の緊急SOSを提供しており、衛星通信企業グローバルスターに累計約20億ドルを出資し、通信容量の85%をiPhone向けに確保する提携を結んでいます [24]。これは将来的なサブスク収益化とエコシステム強化を狙う戦略です [17, 24]。
- **ソフトバンクグループ**:ABBからのロボット事業買収(約80億円)により、「フィジカルAI」を次の成長軸と位置づけました [8]。
- **アサヒグループHD**:サイバー攻撃による工場停止の影響は段階的に解消へ向かっており、流通在庫の正常化とブランド毀損回避のためのコミュニケーションがカギとなります [8]。
- **インターコンチネンタル取引所(ICE)**:暗号資産を用いる予測市場「Polymarket」に20億ドルを出資し、金融取引の主流化に向けた一歩と位置づけています [24]。
V. 投資戦略と今後のチェックリスト
バリュエーションと分散投資の必要性
米株のバリュエーションは歴史比較でも高水準にあり、「史上高値圏での資産価格上昇」「テック主導の集中」「信用・オプション取引の過熱」など、伸びの恩恵と裏腹のリスクが意識されています [17, 22]。
専門家は、期待リターンの低下を意識した資産配分が必要であるとし、グロース一極からの分散(バリューや地域分散、通貨の分散)を促しています [10, 17, 21, 22]。株と金が同時に上がる局面は、インフレ・政策・地政学リスクを織り込みながら「守り」を厚くしている証左であり、上がる局面でも守りを同時に厚くするのが現在の勝ち筋とされています [4, 17]。
短期・中期の展望とチェックリスト
短期(〜10月)の相場は、米国の「データ空白×政策期待」によりブレやすい状態にあり、個別材料や政局ニュースへの反応が増幅しやすい地合いです [8, 10, 21]。
中期的な相場の“質と持続性”を決定する主要なチェックポイントは以下の四点です [4, 10, 15]。
- 米主要企業の決算の質:AI投資の持続性、ROAI(AI投資の収益化)の言及、マージンの耐性 [4, 10]。
- 政策・金利:FRBの利下げペースとデータ遅延の扱い、ウィリアムズ総裁の利下げ支持発言の波及度 [4, 15]。データ空白が続けば、次の政策判断は「遅く、慎重」にシフトし、結果として長期金利のピークアウト観測→リスク資産選好の継続という流れがメインシナリオです [10]。
- 日本の政策運営と物価対応:新政権の財源・工程表・日銀との整合性、長長期金利の上ぶれが株の重石になるかの臨界点 [4, 15]。為替は円安一辺倒から「踊り場」リスクが意識され、イベントドリブンな機動対応が無難とされています [10]。
- コモディティ動向:金・銀高の意味合い(“守り”の厚み) [4, 17]。
投資家は、テーマに偏らない分散と、決算ファクトの検証を軸にしたメリハリのあるリスク管理が有効であると結論づけられています [4, 10, 21]。
VI. 出典情報
出典サイト:
2025年10月10日|経済の見方と今後のマーケット展望 | Chuta-Investment-and-Trading
2025年10月6日|経済の見方と今後のマーケット展望 | Chuta-Investment-and-Trading
2025年10月7日|経済の見方と今後のマーケット展望 | Chuta-Investment-and-Trading
2025年10月8日|経済の見方と今後のマーケット展望 | Chuta-Investment-and-Trading
2025年10月9日|経済の見方と今後のマーケット展望 | Chuta-Investment-and-Trading